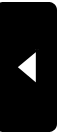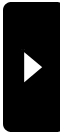2011年01月20日
那覇地区社会教育委員連絡協議会
平成22年度那覇地区社会教育委員連絡協議会が
1月27日(木)14:00~17:00に開催されます。
 テーマ:
テーマ:
「地域ぐるみで育てよう」~子育ては親育て~
 場所:
場所:
浦添市男女共同参画推進ハーモニーセンター 2階第1会議室
浦添市安波茶2-3-5
 内容:
内容:
・第40回九州ブロック社会教育研究大会(佐賀大会)参加報告
浦添市社会教育委員 長田隆子氏
・講演会テーマ「家庭教育の果たす役割とはなにか」~子育ては親育て~
講師 生形泰子氏(財団法人 野村生涯教育センター)
 参加対象:
参加対象:
那覇地区(那覇市、浦添市、南大東村、久米島町)社会教育委員及び
社会教育指導員、公民館職員、社会教育行政関係者、県教育庁関係職員
 主催:
主催:
那覇地区社会教育委員連絡協議会
 申し込み先 1月26日(水)まで
申し込み先 1月26日(水)まで
那覇地区社会教育委員連絡協議会事務局 (久米島町教育委員会内)
担当:平良朝春
TEL:098-985-2287 FAX:098-985-2856
a-taira◆town.kumejima.okinawa.jp
⇒◆を@に変えて送信してください。
1月27日(木)14:00~17:00に開催されます。
 テーマ:
テーマ:「地域ぐるみで育てよう」~子育ては親育て~
 場所:
場所:浦添市男女共同参画推進ハーモニーセンター 2階第1会議室
浦添市安波茶2-3-5
 内容:
内容:・第40回九州ブロック社会教育研究大会(佐賀大会)参加報告
浦添市社会教育委員 長田隆子氏
・講演会テーマ「家庭教育の果たす役割とはなにか」~子育ては親育て~
講師 生形泰子氏(財団法人 野村生涯教育センター)
 参加対象:
参加対象:那覇地区(那覇市、浦添市、南大東村、久米島町)社会教育委員及び
社会教育指導員、公民館職員、社会教育行政関係者、県教育庁関係職員
 主催:
主催:那覇地区社会教育委員連絡協議会
 申し込み先 1月26日(水)まで
申し込み先 1月26日(水)まで那覇地区社会教育委員連絡協議会事務局 (久米島町教育委員会内)
担当:平良朝春
TEL:098-985-2287 FAX:098-985-2856
a-taira◆town.kumejima.okinawa.jp
⇒◆を@に変えて送信してください。
2011年01月19日
開催します『社会教育委員等 研修会(中頭地区)』
平成23年2月10日(木)に、
社会教育委員等研修会(中頭地区)を北中城村の
あやかりの杜にて開催します。

インタビュー・ダイアローグ方式で、
「今必要とされている、社会教育委員の役割とは?」というテーマに沿って
 インタビューアー:
インタビューアー:
井上講四さん(琉球大学生涯学習教育研究センター長・教育学部教授)
森田孟則さん(沖縄県社会教育委員)
 登 壇 者 :社会教育委員(1年目の方)
登 壇 者 :社会教育委員(1年目の方)
内間幸枝さん(1年目 うるま市社会教育委員)
大城 健さん(1年目 北中城村社会教育委員)
知花昌美さん(1年目 読谷村社会教育委員)
洲鎌 武夫さん(1年目 嘉手納町社会教育委員)
井上講四氏、森田孟則氏が社会教育委員のみなさんに
インタビューをしながらお答えいただく形で進めます。
少し目新しく、臨場感あふれる研修会になる予定です。
ぜひお越しください。









平成22年度 社会教育委員等 研修会(中頭地区)
1. 趣旨
「社会教育委員として何をすべきか」という悩みをお互いに掘り起こし、
これからの社会教育の諸課題に対応すべく、実際生活に関わる、
各自のそれまでの経験、能力等の活かし方を考える機会とする。
また、各自の疑問や課題を明確にし、今後の研修会の組み立ての参考にすることで、
次年度沖縄県で開催の社会教育研究大会九州大会につなげる。
2. テーマ
「社会教育委員として実感の持てる在り方とは」
~経験を活かした積極的な関わり方を目指して~
3. 主催
NPO法人なはまちづくりネット(沖縄県委託事業 社会教育委員等資質向上支援事業)
4. 期日
平成23年2月10日(木)14:00~16:30(受付13:30~14:00)
5. 場所
あやかりの杜 多目的ホール
6.参加対象
社会教育に携わる方ならどなたでも
社会教育委員、社会教育指導員、社会教育主事、図書館職員、公民館職員、学校関係者
7. 内容
(1) 開会行事
(2) インタビュー・ダイアローグ「今必要とされている、社会教育委員の役割とは?」
インタビューアー:
井上講四氏 (琉球大学生涯学習教育研究センター長・教育学部教授)
+森田孟則さん(沖縄県社会教育委員)
+ 社会教育委員(1~2年目の方)北中城村・うるま市・読谷村・嘉手納町
※井上先生が社会教育委員のみなさんにインタビューをしながらお答えいただく形。
(3) 質疑及び意見交換
(4) 閉会
8. 参加方法
別紙「参加申込用紙」に記入の上、ご提出ください。(FAXもしくはEメール)
申込締め切り 2月8日(火)
9. 問合せ先
〒902-0073 沖縄県那覇市上間563 TEL/FAX:098-832-9966
メール gakushin.namane◆gmail.com
⇒◆を@に変えて送信してください。
◆詳細はこちらからもどうぞ>> ※PDFが開きます。
社会教育委員等研修会(中頭地区)を北中城村の
あやかりの杜にて開催します。

インタビュー・ダイアローグ方式で、
「今必要とされている、社会教育委員の役割とは?」というテーマに沿って
 インタビューアー:
インタビューアー:井上講四さん(琉球大学生涯学習教育研究センター長・教育学部教授)
森田孟則さん(沖縄県社会教育委員)
 登 壇 者 :社会教育委員(1年目の方)
登 壇 者 :社会教育委員(1年目の方)内間幸枝さん(1年目 うるま市社会教育委員)
大城 健さん(1年目 北中城村社会教育委員)
知花昌美さん(1年目 読谷村社会教育委員)
洲鎌 武夫さん(1年目 嘉手納町社会教育委員)
井上講四氏、森田孟則氏が社会教育委員のみなさんに
インタビューをしながらお答えいただく形で進めます。
少し目新しく、臨場感あふれる研修会になる予定です。
ぜひお越しください。









平成22年度 社会教育委員等 研修会(中頭地区)
1. 趣旨
「社会教育委員として何をすべきか」という悩みをお互いに掘り起こし、
これからの社会教育の諸課題に対応すべく、実際生活に関わる、
各自のそれまでの経験、能力等の活かし方を考える機会とする。
また、各自の疑問や課題を明確にし、今後の研修会の組み立ての参考にすることで、
次年度沖縄県で開催の社会教育研究大会九州大会につなげる。
2. テーマ
「社会教育委員として実感の持てる在り方とは」
~経験を活かした積極的な関わり方を目指して~
3. 主催
NPO法人なはまちづくりネット(沖縄県委託事業 社会教育委員等資質向上支援事業)
4. 期日
平成23年2月10日(木)14:00~16:30(受付13:30~14:00)
5. 場所
あやかりの杜 多目的ホール
6.参加対象
社会教育に携わる方ならどなたでも
社会教育委員、社会教育指導員、社会教育主事、図書館職員、公民館職員、学校関係者
7. 内容
(1) 開会行事
(2) インタビュー・ダイアローグ「今必要とされている、社会教育委員の役割とは?」
インタビューアー:
井上講四氏 (琉球大学生涯学習教育研究センター長・教育学部教授)
+森田孟則さん(沖縄県社会教育委員)
+ 社会教育委員(1~2年目の方)北中城村・うるま市・読谷村・嘉手納町
※井上先生が社会教育委員のみなさんにインタビューをしながらお答えいただく形。
(3) 質疑及び意見交換
(4) 閉会
8. 参加方法
別紙「参加申込用紙」に記入の上、ご提出ください。(FAXもしくはEメール)
申込締め切り 2月8日(火)
9. 問合せ先
〒902-0073 沖縄県那覇市上間563 TEL/FAX:098-832-9966
メール gakushin.namane◆gmail.com
⇒◆を@に変えて送信してください。
◆詳細はこちらからもどうぞ>> ※PDFが開きます。
2011年01月17日
九州地区公民館研究大会 沖縄大会(追加情報)
去る2010年11月10日・11日に開催された
第61回九州地区公民館研究大会 沖縄大会の追加情報です。
那覇市立若狭公民館のHPに
第5分科会「地域づくり」の様子が動画で載っています。
ぜひご覧下さい。(トップページ右下あたり)
那覇市若狭公民館HP>>
若狭公民館の広報紙「広報わかさ NO.71」でも、分科会での取り組みについて紹介されています。
http://naha-kouminkan.city.naha.okinawa.jp/wak-kou/pdf/kw71.pdf
※PDFが開きます。




また、那覇市立中央公民館が発行している広報誌「相思樹」に
公民館大会の様子が載っています。
広報誌「相思樹」2010.12.24発行>>
※PDFが開きます。
第61回九州地区公民館研究大会 沖縄大会の追加情報です。
那覇市立若狭公民館のHPに
第5分科会「地域づくり」の様子が動画で載っています。
ぜひご覧下さい。(トップページ右下あたり)
那覇市若狭公民館HP>>
若狭公民館の広報紙「広報わかさ NO.71」でも、分科会での取り組みについて紹介されています。
http://naha-kouminkan.city.naha.okinawa.jp/wak-kou/pdf/kw71.pdf
※PDFが開きます。




また、那覇市立中央公民館が発行している広報誌「相思樹」に
公民館大会の様子が載っています。
広報誌「相思樹」2010.12.24発行>>
※PDFが開きます。
2011年01月17日
学校支援ボランティア等研修会
平成22年度 沖縄県学校支援地域本部事業
学校支援ボランティア等研修会が開催されました。

※学校支援地域本部事業ハンドブックはこちら>>
平成23年1月14日(金)14:00~
場 所 沖縄県総合福祉センター ゆいホール
内 容 ・事例発表(ボランティア・コーディネーター・担当職員から)
主 催 沖縄県教育委員会
協 力 沖縄県学びをつくる研究会
対 象
「学校支援地域本部事業」地域コーディネーター、市町村教育委員会担当者、
学校関係者(校長・教頭・地域連携担当・ボランティア担当等)、
PTA、学校支援ボランティア、ボランティア団体関係者等、
県運営協議会委員、各教育事務所社会教育主事
→当日、120名の参加でした。

報告
●趣 旨
・「学校支援地域本部事業」に関わる地域コーディネーターや学校支援ボランティア活動者及び教員等が一堂に会し、事例発表等をとおして、地域と学校の連携の在り方や方策等についての理解を深める。
・地域コーディネーター、学習支援ボランティア、教育委員会担当者、教員等の資質向上や事業の充実に資する。
【内容】
事例発表、質疑応答、シンポジウム
事例発表①
うるま市立具志川小学校 ボランティア わかば会 会長 島袋房雄
・事業の経緯
県の平成20年度学校支援地域本部事業の導入に伴い、うるま市では平成21年10月より事業申請をし、その事業が円滑に行われるように、うるま市学校支援地域本部事業実行委員会を立ち上げ、うるま市具志川小学校の一校で進めている。
・うるま市の学校支援地域本部事業実行委員会は13名で構成されている。教育部長、指導部長、学校長、教頭、(具志川小)、老人会、わかば会会長、こども会会長、PTA環境整備部長、ちゅら海代表(読み聞かせ)、社会教育主事、コーディネーター
・活動内容は
会議の開催(活動内容の検討、事業の理解と協力、活動の報告等)
広報活動(ボランティアへの協力依頼のチラシ、生涯学習フェスティバルで展示発表)
・ボランティアの登録数は、保護者32名、地域の方 61名(中学生・高校生各2名ずつ含む)、合計93名。
・成果
【学校】
① 裁縫や習字、発声指導等、地域の方の経験者による指導のもと学習が充実した。
② 花壇等の手入れが日常化し、学校がきれいになった。
③ 地域との連携がスムーズになり、学校のニーズに対応した地域人材を効果的に活用できている。
【児童】
① 読み聞かせが楽しみである。
② ボイストレーニングにより発声が上達し、発表力も向上した。
③ こがねの杜がきれいになって、明るくなり陽が差してきた。
【ボランティア】
① ボランティア員になり、児童と接する機会が増え自分も元気になり学校に貢献できることに生きがいを感じている。
② 町なかでも、子どもたちから挨拶をしてもらうのがうれしく、「やめられないなぁ」という気持ち。
⇒課題
① 多様な人材登録のために地域(自治会)との連携が必要である。
② 学校支援の主な参加者(わかば会)は、高齢者が多く、継続するためにも後継者作りが必要である。
事例発表②
宮古島市立平良中学校区コーディネーター 上松朋子
・宮古島市は平成20年より実行委員会設置。
・平良中校区(平良中・平良第一小・南小)
・佐良浜中校区(佐良浜中・佐良浜小)
⇒3名のコーディネーターで支援
・朝の交通安全運動は予算化されている(帽子・ジャケットの支給)
・宮古島市の特色ある事例(伝統文化)
●十五夜のシーシャー(シーサー)づくりと十五夜の行事についての学習(南小)
●水泳教室(水温が18度以下にならない限り12月も実施)(平良中校区)
●クイチャー指導(佐良浜小)・・・クイチャー=伝統芸能
●ミャークヅツの講話(佐良浜小)・・・ミャークヅツ=伝統文化
●部活動の指導(平良第一小)
●ハーリーについての講話(佐良浜小)
●休日の花壇の水やり(佐良浜小・中)
・若い学校の先生に「少し手伝ったら次からもっとしないといけないじゃないか」という声に驚いた。
・大学生の層が島にいないことから、今年二月の取り組みとして、琉球大学からなるべく宮古島出身の学生に来てもらい、「知のふるさと納税(by琉球大学 背戸教授)」として、大学生との交流事業を行う。
・もともと地域と学校の連携など、出来ていた部分があるので、この事業(学校支援地域本部事業)により複雑になった部分があるかもしれない。
事例発表③
南風原町教育委員会 学校支援地域本部事業担当 山中安麿
・事業の経緯
南風原町では平成21年度から学校支援地域本部事業に取り組んでいる。町内には2中学校、4小学校があり、2名の地域コーディネーターが中学校区ごとに分かれて活動している。
対象校:南風原中学校区 南風原中学校・南風原小学校・北丘小学校
南 星中学校区 南星中学校・津嘉山小学校・翔南小学校
・地域コーディネーターの活動(2名)
① 地域の方々に顔を覚えてもらう
② 学校の先生方に顔を覚えてもらう
③ 学校からの要望によってコーディネートしていく
例:中央公民館ミシンサークルによるミシン指導
・・・学校のミシンの修理について助言があった。
老人クラブによる昔遊び指導
PTAによるプール監視・水泳指導
地域住民による地域学習やキャリア学習等
退職教員や大学生によるワンカラ塾(放課後学習支援)
④ コーディネート後の感想や意見のまとめ
授業に参加した子ども達、学校の先生、関わってくださったボランティア等
⇒手作り料理を作っての懇談会
それぞれの学校での取り組みの紹介を通じて、より積極的な事業の活用を狙って実施。
ボランティア参加者約80名、学校・行政関係者30名の会となった。
◆シンポジウム
テーマ「学校支援ボランティアの可能性と方向性」
◆コーディネーター
琉球大学教育学部教授、沖縄県学校支援地域本部運営協議会 会長 井上講四
◆シンポジスト
那覇市立石嶺中学校 校長 屋部 文幹
那覇市立石嶺中学校コーディネーター 嘉数清美
沖縄県学びをつくる研究会 会長 真喜志 昇
沖縄県教育庁生涯学習振興課 学校支援地域本部担当 宇都宮 幸雄

・井上講四氏がインタビュアーとなり、4名に質問をしながら進める、インタビューダイヤログ方式で行われた。那覇市立石嶺中学校校長 屋部文幹氏からは「PTAと学校支援ボランティアとの線引きなんてする必要はない」と発言があり、今年度からの校長だが、この事業を積極的に進め、地域の人にどんどん学校に入ってもらっている様子がうかがえた。また、PTA事務を4年間経験している那覇市立石嶺中学校コーディネーター 嘉数清美氏からは「校長だけでなく、先生1人1人がボランティアを受け入れるように」との言葉があり、学校に頻繁に出入りする中で見えてくる、熱心な校長とは裏腹に学校の教員1人1人の意識向上を願う発言が目立った。沖縄県教育庁生涯学習振興課 学校支援地域本部担当 宇都宮幸雄氏からは本事業の成果と課題について発表があった。
●成果
・教員がより教育活動に力を注ぐことが出来るようになった。
・地域住民と子どものコミュニケーションが図れ、地域のきずなを深めることが出来た。
・地域の教育力を高めることが出来た。(生涯学習社会)
●課題
・市町村、学校単位での地域教育協議会の活性化
・地域コーディネーター役となる人材の確保
・コーディネーター、ボランティアの資質向上
・ボランティアの登録人数を増やす。
学校支援ボランティア等研修会が開催されました。

※学校支援地域本部事業ハンドブックはこちら>>
平成23年1月14日(金)14:00~
場 所 沖縄県総合福祉センター ゆいホール
内 容 ・事例発表(ボランティア・コーディネーター・担当職員から)
主 催 沖縄県教育委員会
協 力 沖縄県学びをつくる研究会
対 象
「学校支援地域本部事業」地域コーディネーター、市町村教育委員会担当者、
学校関係者(校長・教頭・地域連携担当・ボランティア担当等)、
PTA、学校支援ボランティア、ボランティア団体関係者等、
県運営協議会委員、各教育事務所社会教育主事
→当日、120名の参加でした。

報告
●趣 旨
・「学校支援地域本部事業」に関わる地域コーディネーターや学校支援ボランティア活動者及び教員等が一堂に会し、事例発表等をとおして、地域と学校の連携の在り方や方策等についての理解を深める。
・地域コーディネーター、学習支援ボランティア、教育委員会担当者、教員等の資質向上や事業の充実に資する。
【内容】
事例発表、質疑応答、シンポジウム
事例発表①
うるま市立具志川小学校 ボランティア わかば会 会長 島袋房雄
・事業の経緯
県の平成20年度学校支援地域本部事業の導入に伴い、うるま市では平成21年10月より事業申請をし、その事業が円滑に行われるように、うるま市学校支援地域本部事業実行委員会を立ち上げ、うるま市具志川小学校の一校で進めている。
・うるま市の学校支援地域本部事業実行委員会は13名で構成されている。教育部長、指導部長、学校長、教頭、(具志川小)、老人会、わかば会会長、こども会会長、PTA環境整備部長、ちゅら海代表(読み聞かせ)、社会教育主事、コーディネーター
・活動内容は
会議の開催(活動内容の検討、事業の理解と協力、活動の報告等)
広報活動(ボランティアへの協力依頼のチラシ、生涯学習フェスティバルで展示発表)
・ボランティアの登録数は、保護者32名、地域の方 61名(中学生・高校生各2名ずつ含む)、合計93名。
・成果
【学校】
① 裁縫や習字、発声指導等、地域の方の経験者による指導のもと学習が充実した。
② 花壇等の手入れが日常化し、学校がきれいになった。
③ 地域との連携がスムーズになり、学校のニーズに対応した地域人材を効果的に活用できている。
【児童】
① 読み聞かせが楽しみである。
② ボイストレーニングにより発声が上達し、発表力も向上した。
③ こがねの杜がきれいになって、明るくなり陽が差してきた。
【ボランティア】
① ボランティア員になり、児童と接する機会が増え自分も元気になり学校に貢献できることに生きがいを感じている。
② 町なかでも、子どもたちから挨拶をしてもらうのがうれしく、「やめられないなぁ」という気持ち。
⇒課題
① 多様な人材登録のために地域(自治会)との連携が必要である。
② 学校支援の主な参加者(わかば会)は、高齢者が多く、継続するためにも後継者作りが必要である。
事例発表②
宮古島市立平良中学校区コーディネーター 上松朋子
・宮古島市は平成20年より実行委員会設置。
・平良中校区(平良中・平良第一小・南小)
・佐良浜中校区(佐良浜中・佐良浜小)
⇒3名のコーディネーターで支援
・朝の交通安全運動は予算化されている(帽子・ジャケットの支給)
・宮古島市の特色ある事例(伝統文化)
●十五夜のシーシャー(シーサー)づくりと十五夜の行事についての学習(南小)
●水泳教室(水温が18度以下にならない限り12月も実施)(平良中校区)
●クイチャー指導(佐良浜小)・・・クイチャー=伝統芸能
●ミャークヅツの講話(佐良浜小)・・・ミャークヅツ=伝統文化
●部活動の指導(平良第一小)
●ハーリーについての講話(佐良浜小)
●休日の花壇の水やり(佐良浜小・中)
・若い学校の先生に「少し手伝ったら次からもっとしないといけないじゃないか」という声に驚いた。
・大学生の層が島にいないことから、今年二月の取り組みとして、琉球大学からなるべく宮古島出身の学生に来てもらい、「知のふるさと納税(by琉球大学 背戸教授)」として、大学生との交流事業を行う。
・もともと地域と学校の連携など、出来ていた部分があるので、この事業(学校支援地域本部事業)により複雑になった部分があるかもしれない。
事例発表③
南風原町教育委員会 学校支援地域本部事業担当 山中安麿
・事業の経緯
南風原町では平成21年度から学校支援地域本部事業に取り組んでいる。町内には2中学校、4小学校があり、2名の地域コーディネーターが中学校区ごとに分かれて活動している。
対象校:南風原中学校区 南風原中学校・南風原小学校・北丘小学校
南 星中学校区 南星中学校・津嘉山小学校・翔南小学校
・地域コーディネーターの活動(2名)
① 地域の方々に顔を覚えてもらう
② 学校の先生方に顔を覚えてもらう
③ 学校からの要望によってコーディネートしていく
例:中央公民館ミシンサークルによるミシン指導
・・・学校のミシンの修理について助言があった。
老人クラブによる昔遊び指導
PTAによるプール監視・水泳指導
地域住民による地域学習やキャリア学習等
退職教員や大学生によるワンカラ塾(放課後学習支援)
④ コーディネート後の感想や意見のまとめ
授業に参加した子ども達、学校の先生、関わってくださったボランティア等
⇒手作り料理を作っての懇談会
それぞれの学校での取り組みの紹介を通じて、より積極的な事業の活用を狙って実施。
ボランティア参加者約80名、学校・行政関係者30名の会となった。
◆シンポジウム
テーマ「学校支援ボランティアの可能性と方向性」
◆コーディネーター
琉球大学教育学部教授、沖縄県学校支援地域本部運営協議会 会長 井上講四
◆シンポジスト
那覇市立石嶺中学校 校長 屋部 文幹
那覇市立石嶺中学校コーディネーター 嘉数清美
沖縄県学びをつくる研究会 会長 真喜志 昇
沖縄県教育庁生涯学習振興課 学校支援地域本部担当 宇都宮 幸雄

・井上講四氏がインタビュアーとなり、4名に質問をしながら進める、インタビューダイヤログ方式で行われた。那覇市立石嶺中学校校長 屋部文幹氏からは「PTAと学校支援ボランティアとの線引きなんてする必要はない」と発言があり、今年度からの校長だが、この事業を積極的に進め、地域の人にどんどん学校に入ってもらっている様子がうかがえた。また、PTA事務を4年間経験している那覇市立石嶺中学校コーディネーター 嘉数清美氏からは「校長だけでなく、先生1人1人がボランティアを受け入れるように」との言葉があり、学校に頻繁に出入りする中で見えてくる、熱心な校長とは裏腹に学校の教員1人1人の意識向上を願う発言が目立った。沖縄県教育庁生涯学習振興課 学校支援地域本部担当 宇都宮幸雄氏からは本事業の成果と課題について発表があった。
●成果
・教員がより教育活動に力を注ぐことが出来るようになった。
・地域住民と子どものコミュニケーションが図れ、地域のきずなを深めることが出来た。
・地域の教育力を高めることが出来た。(生涯学習社会)
●課題
・市町村、学校単位での地域教育協議会の活性化
・地域コーディネーター役となる人材の確保
・コーディネーター、ボランティアの資質向上
・ボランティアの登録人数を増やす。
2011年01月06日
第52回沖縄県社会教育研究大会 1/28
新年あけましておめでとうございます。
1月は、沖縄県社会教育研究大会が開催されます。
午前中の講演の講師、正平辰男さんのお話を
昨年10月の九州ブロック社会教育研究大会 佐賀大会にて
聴いてきたのですが、とっても面白く、会場は笑いに包まれていました。
実践者だからこその言葉は説得力がありますね。
多くの方で参加しましょう。
日時:平成23年1月28日(金)9:30~15:15
会場:豊見城市中央公民館 第ホール
大会テーマ:青少年が健全に育つ地域づくりと社会教育の役割

1月は、沖縄県社会教育研究大会が開催されます。
午前中の講演の講師、正平辰男さんのお話を
昨年10月の九州ブロック社会教育研究大会 佐賀大会にて
聴いてきたのですが、とっても面白く、会場は笑いに包まれていました。
実践者だからこその言葉は説得力がありますね。
多くの方で参加しましょう。
日時:平成23年1月28日(金)9:30~15:15
会場:豊見城市中央公民館 第ホール
大会テーマ:青少年が健全に育つ地域づくりと社会教育の役割

2010年12月27日
広報誌「社会教育の風 沖縄から」Vol.8 発行しました。
広報誌「社会教育の風 沖縄から」8号を発行しました。
今回の内容は・・・
◆10月~12月の社会教育関係の研修会
◆九州ブロック社会教育研究大会(佐賀大会)
◆全国社会教育研究大会
等の取材記録です。

*写真は11月29日名護市羽根地地区センター
沖縄県公共図書館連絡協議会のもようです。
幅広い方に読んでいただきたく、
各市町村の社会教育委員、社会教育指導員、
図書館、その他社会教育関係のみなさんにお送りしています。
本日から随時発送いたしておりますので、今しばらくお待ちください。
発送する広報誌は白黒印刷なのですが、
こちらからはカラーでダウンロード出来ますので、ぜひどうぞ。
(1ページずつで申し訳ありません )
)
P1>>
P2>>
P3>>
P4>>
P5>>
P6>>
P7>>
P8>>








今回の内容は・・・
◆10月~12月の社会教育関係の研修会
◆九州ブロック社会教育研究大会(佐賀大会)
◆全国社会教育研究大会
等の取材記録です。

*写真は11月29日名護市羽根地地区センター
沖縄県公共図書館連絡協議会のもようです。
幅広い方に読んでいただきたく、
各市町村の社会教育委員、社会教育指導員、
図書館、その他社会教育関係のみなさんにお送りしています。
本日から随時発送いたしておりますので、今しばらくお待ちください。
発送する広報誌は白黒印刷なのですが、
こちらからはカラーでダウンロード出来ますので、ぜひどうぞ。
(1ページずつで申し訳ありません
 )
)P1>>
P2>>
P3>>
P4>>
P5>>
P6>>
P7>>
P8>>








2010年12月03日
島尻地区社会教育研究大会
平成22年度島尻地区社会教育研究大会が12/2(木)
南部総合福祉センターにて開催されました。
テーマ:「地域における社会教育の活性化を目指して~担い手をどう育てるか~」
趣旨:島尻地区の社会教育委員及び社会教育関係者が一堂に会し、市町村における社会教育の現状や研究の成果や課題について情報交換を行い、地域における社会教育の活性化を図り、各市町村の生涯学習・社会教育の充実、発展に資する。
講演、事例発表、質疑・意見交換
(1)講師:津留 健二氏 沖縄女子短期大学客員教授
演題:『明日を拓く社会教育への期待 ~化石のつぶやき~』

(2)事例発表
①「座間味村における社会教育」 座間味村社会教育委員 宮平善孝
②「社会教育委員の役割」 与那原町社会教育委員 根川清義
(3)質疑及び意見交換
(4)まとめ 南城市社会教育委員 山内美武
基調講演
・女子学生と話していると言っていることがわからないことが度々あり、意味を尋ねると「先生は化石だ」「私たちは新・新人類だ」という会話があることから演題「化石のつぶやき」が付いた。
・知念高校の教師から行政へ。当初決まっていた学校指導課が機構改革でなくなり、社会教育課長として配属。学校はカリキュラムがあり、路線が決まっていたが、社会教育はとても柔軟なことに驚いた。積極的にやる気がなければ務まらない、と。学校だけではワンパターンになる。今、話していても元先生だっただろうと言われることがある。学校を「同質性の満足」と言うなら、社会教育は「異質性の満足」(異質な人との交わりで満足する)と言える。
・社会教育に関わる人は、今日の社会状況を把握する必要があり、その上で社会教育に活かしていくべき。
・中央教育審議会の平成20年度の答申をはじめ、最近は「新しい」とタイトルについていることが多い。新しい時代とは何か。昔は「貧しさに処する教育」がなされていたが今は「豊かさに処する教育」がされている。過剰な豊かさが生む新しい貧しさがある。経済学はこの豊かさを求めてきたが、この貧しさは経済学が解決できない。
・教育基本法を読んでいない教師や社会教育関係者が多い。まず読むことから始めよう。18カ条中7つが社会教育について書かれているので。
・沖縄の子どもの長所は「明るい・素直・思いやりがある」短所は「けじめのある生活がない・一人勉強ができない・根気強さがない」
・高校生には3つの願いを伝えてきた①自ら、日常生活を点検できる力②自ら、学ぶ意欲の力③自ら、未来につながる力
・学習指導要領では「生きる力」が言われているが、沖縄では「ジンブン」を身につけることが大切である。
・ひめゆりの塔は今や観光地だ。ほとんどが県外からの修学旅行生。時間に追われて通り過ぎるだけなので、これからは「点」から「線」の修学旅行を目指す。
・青年の家を活用することも含めて、いかに地域の特性をつかんで取り入れるかが、市民に対するサービスなのではないか。
・学歴中心だった以前から、今は「資格社会」。あなたは何ができますか?という社会だ。
・今、国民総出で日本の教育を考える必要性がある。生涯学習社会を成り立たせるには「自発的な意思」が必要。
・2011年1月より、沖縄県でも県民カレッジで社会教育主事講習が受けられるようになったが、(締め切りはこの前日)島尻地区、国頭地区からの参加者はゼロ。全体で10名。栃木県では毎年40名が主事資格を取り、各施設にいる人はみな有資格者である。
・生涯学習推進会議に最近参加したが、有名無実。みんなお客さんになっている。「お手伝いじゃない、自分の仕事だ」と言ってきたのだが・・。
・東京都杉並区の杉並会館は高校生に設計させており、小中学生も来やすい施設を目指した。ワンフロアは清涼飲料水とお菓子を食べながら交流するスペース。コンビニ前でたむろしていた子たちも他行との交流の場になっている。担当者は毎日学校に訪問し、報告している。
・大阪では24時間オープンの青年が集まる場があり、あらゆる社会教育団体の案内が置いてある。沖縄では10時に帰る運動を頑張っていると言うと笑われた。若者のパワーを発散させる場を作らねば、とのこと。
・今日は私が前に立ち教えているが、明日はみなさんが教える側に。相互学習をしましょう。経験知を共有しましょう、ベテランから若者へ受け継ぎましょう。キーワードは「つなぐこと」。島自治地区は茶道にもっと力を入れるべき。「動」には力が入っているが「静」にはいまいち力が入っていない。

★津留先生からのおすすめの一冊★
(社会教育委員の方、必携の書)はこちら・・
「新しい時代を創る社会教育」
●「座間味村における社会教育」 座間味村社会教育委員 宮平善孝氏
・座間味村は発表者のスライドが届いていないというハプニングがあったが、ユーモアあふれる発表となった。6~8月は「大和」が来るので人口が増え1000名を超すが平均すると920名程度。産業や歴史、文化を紹介したあと、座間味村の社会教育事業を紹介。文化芸術活動の素晴らしさを知る機会の充実のため、落語家を招いたり、少年の主張大会、各種スポーツ大会等を発表した。今後の課題として、座間味村には公民館が一館もないことに触れ、社会教育推進のため、早急に設置を願うとの意見が述べられた。
●「社会教育委員の役割」 与那原町社会教育委員 根川清義氏
・ジュニアリーダークラブ、敬老会、新島でいご子ども会、演武指導等の取り組みをスライドで紹介。地域の人が行事に参加する人数が減ってきている状況はあるが、幸いにこの地区ではPTA、子ども会、老人会も活発で地域行事に積極的に協力してくれる。ゆっくりあせらずにリーダーを育成していきたい、と述べた。
●第40回九州ブロック社会教育研究大会(佐賀大会)の報告が
島尻地区社会教育委員連絡協議会会長の久保田暁氏よりありました。

南部総合福祉センターにて開催されました。
テーマ:「地域における社会教育の活性化を目指して~担い手をどう育てるか~」
趣旨:島尻地区の社会教育委員及び社会教育関係者が一堂に会し、市町村における社会教育の現状や研究の成果や課題について情報交換を行い、地域における社会教育の活性化を図り、各市町村の生涯学習・社会教育の充実、発展に資する。
講演、事例発表、質疑・意見交換
(1)講師:津留 健二氏 沖縄女子短期大学客員教授
演題:『明日を拓く社会教育への期待 ~化石のつぶやき~』

(2)事例発表
①「座間味村における社会教育」 座間味村社会教育委員 宮平善孝
②「社会教育委員の役割」 与那原町社会教育委員 根川清義
(3)質疑及び意見交換
(4)まとめ 南城市社会教育委員 山内美武
基調講演
・女子学生と話していると言っていることがわからないことが度々あり、意味を尋ねると「先生は化石だ」「私たちは新・新人類だ」という会話があることから演題「化石のつぶやき」が付いた。
・知念高校の教師から行政へ。当初決まっていた学校指導課が機構改革でなくなり、社会教育課長として配属。学校はカリキュラムがあり、路線が決まっていたが、社会教育はとても柔軟なことに驚いた。積極的にやる気がなければ務まらない、と。学校だけではワンパターンになる。今、話していても元先生だっただろうと言われることがある。学校を「同質性の満足」と言うなら、社会教育は「異質性の満足」(異質な人との交わりで満足する)と言える。
・社会教育に関わる人は、今日の社会状況を把握する必要があり、その上で社会教育に活かしていくべき。
・中央教育審議会の平成20年度の答申をはじめ、最近は「新しい」とタイトルについていることが多い。新しい時代とは何か。昔は「貧しさに処する教育」がなされていたが今は「豊かさに処する教育」がされている。過剰な豊かさが生む新しい貧しさがある。経済学はこの豊かさを求めてきたが、この貧しさは経済学が解決できない。
・教育基本法を読んでいない教師や社会教育関係者が多い。まず読むことから始めよう。18カ条中7つが社会教育について書かれているので。
・沖縄の子どもの長所は「明るい・素直・思いやりがある」短所は「けじめのある生活がない・一人勉強ができない・根気強さがない」
・高校生には3つの願いを伝えてきた①自ら、日常生活を点検できる力②自ら、学ぶ意欲の力③自ら、未来につながる力
・学習指導要領では「生きる力」が言われているが、沖縄では「ジンブン」を身につけることが大切である。
・ひめゆりの塔は今や観光地だ。ほとんどが県外からの修学旅行生。時間に追われて通り過ぎるだけなので、これからは「点」から「線」の修学旅行を目指す。
・青年の家を活用することも含めて、いかに地域の特性をつかんで取り入れるかが、市民に対するサービスなのではないか。
・学歴中心だった以前から、今は「資格社会」。あなたは何ができますか?という社会だ。
・今、国民総出で日本の教育を考える必要性がある。生涯学習社会を成り立たせるには「自発的な意思」が必要。
・2011年1月より、沖縄県でも県民カレッジで社会教育主事講習が受けられるようになったが、(締め切りはこの前日)島尻地区、国頭地区からの参加者はゼロ。全体で10名。栃木県では毎年40名が主事資格を取り、各施設にいる人はみな有資格者である。
・生涯学習推進会議に最近参加したが、有名無実。みんなお客さんになっている。「お手伝いじゃない、自分の仕事だ」と言ってきたのだが・・。
・東京都杉並区の杉並会館は高校生に設計させており、小中学生も来やすい施設を目指した。ワンフロアは清涼飲料水とお菓子を食べながら交流するスペース。コンビニ前でたむろしていた子たちも他行との交流の場になっている。担当者は毎日学校に訪問し、報告している。
・大阪では24時間オープンの青年が集まる場があり、あらゆる社会教育団体の案内が置いてある。沖縄では10時に帰る運動を頑張っていると言うと笑われた。若者のパワーを発散させる場を作らねば、とのこと。
・今日は私が前に立ち教えているが、明日はみなさんが教える側に。相互学習をしましょう。経験知を共有しましょう、ベテランから若者へ受け継ぎましょう。キーワードは「つなぐこと」。島自治地区は茶道にもっと力を入れるべき。「動」には力が入っているが「静」にはいまいち力が入っていない。

★津留先生からのおすすめの一冊★
(社会教育委員の方、必携の書)はこちら・・
「新しい時代を創る社会教育」
●「座間味村における社会教育」 座間味村社会教育委員 宮平善孝氏
・座間味村は発表者のスライドが届いていないというハプニングがあったが、ユーモアあふれる発表となった。6~8月は「大和」が来るので人口が増え1000名を超すが平均すると920名程度。産業や歴史、文化を紹介したあと、座間味村の社会教育事業を紹介。文化芸術活動の素晴らしさを知る機会の充実のため、落語家を招いたり、少年の主張大会、各種スポーツ大会等を発表した。今後の課題として、座間味村には公民館が一館もないことに触れ、社会教育推進のため、早急に設置を願うとの意見が述べられた。
●「社会教育委員の役割」 与那原町社会教育委員 根川清義氏
・ジュニアリーダークラブ、敬老会、新島でいご子ども会、演武指導等の取り組みをスライドで紹介。地域の人が行事に参加する人数が減ってきている状況はあるが、幸いにこの地区ではPTA、子ども会、老人会も活発で地域行事に積極的に協力してくれる。ゆっくりあせらずにリーダーを育成していきたい、と述べた。
●第40回九州ブロック社会教育研究大会(佐賀大会)の報告が
島尻地区社会教育委員連絡協議会会長の久保田暁氏よりありました。

2010年11月30日
沖縄県図書館連絡協議会(国頭地区開催)
11月29日(月)名護市羽地地区センターにおいて
沖縄県図書館連絡協議会第三回研修会が開催されました。
「社会教育」という広い分野の中にある、図書館の活動を
今回は討議にまでお邪魔させていただき、勉強させていただきました。

テーマ:“待つ”図書館から“攻める”“つながる”図書館へ
~地域の活性化は図書館から~
地域の公共公民館は、住民の自主学習施設及び情報センターとして、
その果たす役割は重要である。
図書館の役割を再認識し、
今後の図書館の運営及び重要性に対する認識を深めることを目的とする。
◆内容
1) 基調講演
講師:鈴木眞理(まこと)氏 青山学院大学 教育人間科学部教授
演題:『生涯学習社会における図書館の役割』
・ダンスのインストラクター(教える側)が生徒(教わる側)を殺人した事件に触れ、教育の在り方に異変があるとした。また、東京の東村山の図書館に来ていたホームレスの男性に騒がしいことを注意された中学生が、閉館後男性を殺害した事件に触れ、図書館の職員は声かけをしていたというがいったい何をしていたのか。本来、本を通して教育をするのが図書館の役目だが今や、人よりモノに対応する専門性を要求するようになってきていないか、と述べた。それは学芸員にも共通して言えるとのこと。
・「元気」「勇気」「感動」などを「もらう」という言い方を昔はしなかった。本来それらは「わいてくるもの」であり、つまり受け身になっていることを表している。
・掃除が下手であることに悩む人が「お掃除教室があれば行くのに」、学んだ知識を確認したい人が「教養を問う検定がもっとあればいいのに」という新聞の投書を例にとり、方法やどこで学ぶかという点に注目が集まっていると述べた。
・博物館の事務所と展示場所が離れていることがたびたびあることに触れ、社会教育施設としての施設のとらえ方と、機能を分化させているということについて、それでも社会教育概念と言えるのか、と述べた。
・また今回のテーマ“待つ”図書館から“攻める”“つながる”図書館へ にも触れ、「待つことが悪いのではなく、攻めなくても良いのでは、いかにして待つかということも重要」とした。
2) グループ討議
いくつかのグループに分かれて自由に討議を行う。
・5名程度のグループごとに討議を行った。
各館の現状報告/「待つ」図書館とはどういうイメージか/「攻める・つながる」図書館になるためにはどういう取り組みが必要か この3点について話し合った。私の班は、名護市、宜野座村、金武町、本部町の図書館職員がメンバーだった。ブックスタートという、乳児健診の場所まで足を運び、母親にも子どもの本との出会いのきっかけを理解してもらい一冊プレゼントするという取り組みを始めた館が目立った。
・全体としては、図書館員は自分も利用者であるという意識が必要、場所をわかりやすくする、館内表示をわかりやすくする、図書館以外のテーマで講演会を行う、図書館サービスを多面的にとらえる、館外へ出ていく、等の意見が挙がった。
・まとめとして、地域の実情に合わせながら、他機関との連携を取っていく必要があるとのことだった。
●国頭地区での開催だったこともあり、北部地域からの参加が多かったようですが、
石垣市からの参加もあり、討議もそれぞれに盛り上がりました。
討議があることにより、参加者が主体的な気持ちで参加でき、
具体的な情報交換をすることにより参加の意義が深まったのではないでしょうか。
●各館から1人も参加していないところも少なくなく、
こうした他館職員との情報交換や意識を向上させる絶好の機会を逃すのは
もったいないのではと感じました。
沖縄県図書館連絡協議会第三回研修会が開催されました。
「社会教育」という広い分野の中にある、図書館の活動を
今回は討議にまでお邪魔させていただき、勉強させていただきました。

テーマ:“待つ”図書館から“攻める”“つながる”図書館へ
~地域の活性化は図書館から~
地域の公共公民館は、住民の自主学習施設及び情報センターとして、
その果たす役割は重要である。
図書館の役割を再認識し、
今後の図書館の運営及び重要性に対する認識を深めることを目的とする。
◆内容
1) 基調講演
講師:鈴木眞理(まこと)氏 青山学院大学 教育人間科学部教授
演題:『生涯学習社会における図書館の役割』
・ダンスのインストラクター(教える側)が生徒(教わる側)を殺人した事件に触れ、教育の在り方に異変があるとした。また、東京の東村山の図書館に来ていたホームレスの男性に騒がしいことを注意された中学生が、閉館後男性を殺害した事件に触れ、図書館の職員は声かけをしていたというがいったい何をしていたのか。本来、本を通して教育をするのが図書館の役目だが今や、人よりモノに対応する専門性を要求するようになってきていないか、と述べた。それは学芸員にも共通して言えるとのこと。
・「元気」「勇気」「感動」などを「もらう」という言い方を昔はしなかった。本来それらは「わいてくるもの」であり、つまり受け身になっていることを表している。
・掃除が下手であることに悩む人が「お掃除教室があれば行くのに」、学んだ知識を確認したい人が「教養を問う検定がもっとあればいいのに」という新聞の投書を例にとり、方法やどこで学ぶかという点に注目が集まっていると述べた。
・博物館の事務所と展示場所が離れていることがたびたびあることに触れ、社会教育施設としての施設のとらえ方と、機能を分化させているということについて、それでも社会教育概念と言えるのか、と述べた。
・また今回のテーマ“待つ”図書館から“攻める”“つながる”図書館へ にも触れ、「待つことが悪いのではなく、攻めなくても良いのでは、いかにして待つかということも重要」とした。
2) グループ討議
いくつかのグループに分かれて自由に討議を行う。
・5名程度のグループごとに討議を行った。
各館の現状報告/「待つ」図書館とはどういうイメージか/「攻める・つながる」図書館になるためにはどういう取り組みが必要か この3点について話し合った。私の班は、名護市、宜野座村、金武町、本部町の図書館職員がメンバーだった。ブックスタートという、乳児健診の場所まで足を運び、母親にも子どもの本との出会いのきっかけを理解してもらい一冊プレゼントするという取り組みを始めた館が目立った。
・全体としては、図書館員は自分も利用者であるという意識が必要、場所をわかりやすくする、館内表示をわかりやすくする、図書館以外のテーマで講演会を行う、図書館サービスを多面的にとらえる、館外へ出ていく、等の意見が挙がった。
・まとめとして、地域の実情に合わせながら、他機関との連携を取っていく必要があるとのことだった。
●国頭地区での開催だったこともあり、北部地域からの参加が多かったようですが、
石垣市からの参加もあり、討議もそれぞれに盛り上がりました。
討議があることにより、参加者が主体的な気持ちで参加でき、
具体的な情報交換をすることにより参加の意義が深まったのではないでしょうか。
●各館から1人も参加していないところも少なくなく、
こうした他館職員との情報交換や意識を向上させる絶好の機会を逃すのは
もったいないのではと感じました。
2010年11月18日
第18回沖縄県社会教育指導員研修会(自主研修)
場所:うるま市勝連地区公民館
開催:11月4日(木)9:00~16:00
県内各市町村の社会教育指導員が一堂に集い、
社会の変化に対応し
各市町村の社会教育・生涯学習の振興と地域の活性化を目指すとともに、
向上心をもって各種事業の企画・立案・実施等に活かせるように
研修及び情報交換を行うことで
社会教育指導員としての資質向上に努めることを趣旨とし、
年に一回開催されています。
今回、台風で一週間延期となりましたが、50名近くが参加しました。
午前中の講話は下條 義明(うるま市与那城平安座自治会長)
「平安座の伝統行事をとおして豊かで住みよい島創りを進める」と題し、
勝連半島と平安座島が橋でつながる前の時代から、
交通の便が良くなった現在までの時代背景と、年中行事を月ごとに紹介。
午後のポスターセッションは今年初めての試みだそう。
各市町村から事業報告のパネルが提出されていました。
例年ゆっくり見る時間がないため、
今年は代表の5市町村の説明を聞きながら全員で質疑を行いました。
各市町村のポスターについては以下をご覧下さい。
2010年11月17日
第61回九州地区公民館研究大会 沖縄大会
平成22年度 第61回九州地区公民館研究大会 沖縄大会が開催されました。
まず1日目、分科会からスタートです。
私は第4分科会に参加しました。テーマは「成人教育」。
会場は那覇市中央公民館でした。
ざっと見渡して、50名ほどの方が参加されていました。
○討議のテーマ
生涯の各時期の学習ニーズ及び豊かな人間性の育成に対応した公民館活動の在り方
○討議の柱
①幅広い年齢層のニーズに応じた学習提供と活用の在り方について
②住民が地域課題を解決する学習活動と意識改革への関わり方について
・・というわけで
事例発表が行われました。
同じ「公民館」と言えども、県ごとに仕組みも構造も違い、
また、課題も規模も異なることを改めて感じました。
しかしながら、お互いの状況を知りあうことによって
参考に出来る部分や、アドバイスできる部分があることもまた
改めて感じました。
司会は沖縄県沖縄大学人文学部 教授 宮城能彦さん。

◆事例発表①
鹿児島県鹿児島市吉田公民館 主査の松永貢さんより
公民館講座で広がる学びの輪~魅力ある学びの場づくりを目指して~
と題し、
鹿児島市の公民館での講座の工夫、課題、成果等が発表されました。
鹿児島市には78の小学校区があり、
これを14の地域公民館で分担しているため、
学校施設を使えるというメリットがある
という点は、沖縄県とは違う特徴があるようでした。
講座で学んだ受講生が自主学習グループの会員となり
継続して学習している人も少なくないことや、
鹿児島市14の地域公民館では、自主学習グループ生が、
学習の成果を活かして講師を務める講座
「市民はつらつ得意技講座」を2講座ずつ開設していることなどが
成果として報告されました。
◆事例発表②
沖縄県読谷村教育委員会生涯学習課文化センター 係長 與那覇徳雄さんより
伝統工芸ヤチムンを通した「生きがい活動支援」と「サークル委託講座」の取り組み
について報告がありました。
返還軍用地跡地利用として沖縄の伝統工芸である
ヤチムン(陶芸)の窯元を招致した『やちむんの里』内に
平成6年生涯学習施設として建造された読谷村陶芸研修所があり、
①村内保育所・小中学校ヤチムン体験」
②「ヤチムンサークル活動(7サークル)」
③「高齢者学級(物作り体験)」
④「ヤチムン出前講座」を行っている。
⑤この中から陶芸研修所まで足を運べない村内の高齢者を対象に、
沖縄の伝統工芸であるヤチムンを通して、
物づくりの楽しさや喜びを感じてもらう生きがいづくりのための
「ヤチムン出前講座」が紹介された。
参加者からは「生きていて良かった(90歳)」
「楽しくて正月と盆が来るくらい楽しみ(80歳)」など好評だそう。
①サークルが積極的に受講者に関わり、
講師対受講生の構図がサークル対受講生に代わり、
互いのスキル向上や親睦の場となった
②限られた施設におけるサークル数が抑えられ有効活用が図られた
③講師への報償費(予算)が抑えられ、
サークルの自主運営により職員にゆとりが生まれた、
などが成果として挙げられていました。
まとめとして、
助言者の鹿児島県NPO法人かごしま生涯サポートセンター理事 石塚勝郎氏より、
課題は「若者・男性」にどう公民館に入ってきてもらうか。
ニーズの開拓は公民館の非常に大きな役目。
男の為の家事・育児の講座は最近減ってきているが、引き続き必要。
・大人の為の公民館から住民の為の公民館へ変わる必要がある。
・受講者が自主講座を運営し、ゆくゆくは講師になるくらいのスキル向上をはかる
・すてき人登録のような「○○が出来ます」の人を登録。
受講者から講師となれるような仕組み作り
・人から学ぶというより、「自分で学ぶ」という姿勢
★学びたいけれど学べない人(忙しかったり、寝たきりだったり、障がいがあり来れなかったり)
や無関心(学ぶ意欲のない人)をどう開拓するか。
様々なすみずみの人が参加しているか。
来れなかった人の為に報告講座を行うことも大事である。
★地域を住みやすくするためには「行政に頼まないと出来ないこと」
「住民で出来ること」の住み分けをきっちりと行う。
地域に絶対に残してほしいもの、絶対に取り入れてほしいものの
アンケートを取ることもひとつだろう。
博多のとある地域で、新規のマンション建設案が立ち上がった地域で、
「そのマンションに入る人が必ず自治会に入る。入らない場合は住民みんなで反対します」
という約束で建設の許可をした、という例を出して
公民館がしてくれないと、誰もしてくれない。
公民館は常に、仕掛け人であってほしい。 と述べました。
印象として、第4分科会は会場からの質問や意見が思いのほか少なかったので
もう少し、この機会を生かして県内外の取り組みを
積極的に取り入れたり、交換する部分があれば良かったのではということが
課題か、と思いました。


会場は中央公民館のサークルの方の作品が並べられ、にぎやかでした。
沖縄のお菓子も準備されており、会場はあたたかい雰囲気でした。


2日目のシンポジウムは県立武道館で開催されました。
900名近い参加者だったようです。
開会式の前に那覇市立壷屋小学校児童による「組踊」がありました。

テーマを「島に根ざそう」とし、
うちな~噺家の藤木勇人氏より記念講演が行われました。
毎年全国ニュースで取り上げられる、那覇の成人式の荒れた様子の報道に触れ、
あれはほんの一面であり、その後ろからごみを拾っている若者がいることや
公民館で開催する成人席は荒れていないことなど、
そのほかにも、沖縄県のイメージとその「ホントのところ」をユーモアを交え話してくださいました。
会場入り口には、沖縄のお菓子の振る舞いコーナーがあり、
心づかいが県外からの参加者にも伝わったのではないでしょうか。

さて、
私は取材ということもあり、最後列で聞いていたのですが、
なんと、残念ながら音割れで聞き取れない部分が多かったです。。
耳に手をかざして耳をすます人が何人もいて、私もしばらくはそうしていました。
しかし、いまいち聞こえない部分は多かったのは残念です。
そのせいだけではないと思うのですが、
半分から後方の方のマナーが非常に気になりました。
途中退席者や床の音に配慮せず大きな音でうろうろする人、
携帯電話の着信音や携帯電話で話す人、
デジタルカメラのデジタル音を何度も鳴らす人など、
エッ?と思うような光景がありました。
若者を公民館に参加させたい、というようなことが多く聞かれる二日間でしたので
ちょっとこれではそんなこと言えるでしょうか・・・と。
憧れられる大人をまずは目指したい、と思いながら会場を後にしました。。
また、1日目の分科会のまとめについて、少しであっても
分かち合いの時間があれば、さらに良かったのではと思いました。
まず1日目、分科会からスタートです。
私は第4分科会に参加しました。テーマは「成人教育」。
会場は那覇市中央公民館でした。
ざっと見渡して、50名ほどの方が参加されていました。
○討議のテーマ
生涯の各時期の学習ニーズ及び豊かな人間性の育成に対応した公民館活動の在り方
○討議の柱
①幅広い年齢層のニーズに応じた学習提供と活用の在り方について
②住民が地域課題を解決する学習活動と意識改革への関わり方について
・・というわけで
事例発表が行われました。
同じ「公民館」と言えども、県ごとに仕組みも構造も違い、
また、課題も規模も異なることを改めて感じました。
しかしながら、お互いの状況を知りあうことによって
参考に出来る部分や、アドバイスできる部分があることもまた
改めて感じました。
司会は沖縄県沖縄大学人文学部 教授 宮城能彦さん。

◆事例発表①
鹿児島県鹿児島市吉田公民館 主査の松永貢さんより
公民館講座で広がる学びの輪~魅力ある学びの場づくりを目指して~
と題し、
鹿児島市の公民館での講座の工夫、課題、成果等が発表されました。
鹿児島市には78の小学校区があり、
これを14の地域公民館で分担しているため、
学校施設を使えるというメリットがある
という点は、沖縄県とは違う特徴があるようでした。
講座で学んだ受講生が自主学習グループの会員となり
継続して学習している人も少なくないことや、
鹿児島市14の地域公民館では、自主学習グループ生が、
学習の成果を活かして講師を務める講座
「市民はつらつ得意技講座」を2講座ずつ開設していることなどが
成果として報告されました。
◆事例発表②
沖縄県読谷村教育委員会生涯学習課文化センター 係長 與那覇徳雄さんより
伝統工芸ヤチムンを通した「生きがい活動支援」と「サークル委託講座」の取り組み
について報告がありました。
返還軍用地跡地利用として沖縄の伝統工芸である
ヤチムン(陶芸)の窯元を招致した『やちむんの里』内に
平成6年生涯学習施設として建造された読谷村陶芸研修所があり、
①村内保育所・小中学校ヤチムン体験」
②「ヤチムンサークル活動(7サークル)」
③「高齢者学級(物作り体験)」
④「ヤチムン出前講座」を行っている。
⑤この中から陶芸研修所まで足を運べない村内の高齢者を対象に、
沖縄の伝統工芸であるヤチムンを通して、
物づくりの楽しさや喜びを感じてもらう生きがいづくりのための
「ヤチムン出前講座」が紹介された。
参加者からは「生きていて良かった(90歳)」
「楽しくて正月と盆が来るくらい楽しみ(80歳)」など好評だそう。
①サークルが積極的に受講者に関わり、
講師対受講生の構図がサークル対受講生に代わり、
互いのスキル向上や親睦の場となった
②限られた施設におけるサークル数が抑えられ有効活用が図られた
③講師への報償費(予算)が抑えられ、
サークルの自主運営により職員にゆとりが生まれた、
などが成果として挙げられていました。
まとめとして、
助言者の鹿児島県NPO法人かごしま生涯サポートセンター理事 石塚勝郎氏より、
課題は「若者・男性」にどう公民館に入ってきてもらうか。
ニーズの開拓は公民館の非常に大きな役目。
男の為の家事・育児の講座は最近減ってきているが、引き続き必要。
・大人の為の公民館から住民の為の公民館へ変わる必要がある。
・受講者が自主講座を運営し、ゆくゆくは講師になるくらいのスキル向上をはかる
・すてき人登録のような「○○が出来ます」の人を登録。
受講者から講師となれるような仕組み作り
・人から学ぶというより、「自分で学ぶ」という姿勢
★学びたいけれど学べない人(忙しかったり、寝たきりだったり、障がいがあり来れなかったり)
や無関心(学ぶ意欲のない人)をどう開拓するか。
様々なすみずみの人が参加しているか。
来れなかった人の為に報告講座を行うことも大事である。
★地域を住みやすくするためには「行政に頼まないと出来ないこと」
「住民で出来ること」の住み分けをきっちりと行う。
地域に絶対に残してほしいもの、絶対に取り入れてほしいものの
アンケートを取ることもひとつだろう。
博多のとある地域で、新規のマンション建設案が立ち上がった地域で、
「そのマンションに入る人が必ず自治会に入る。入らない場合は住民みんなで反対します」
という約束で建設の許可をした、という例を出して
公民館がしてくれないと、誰もしてくれない。
公民館は常に、仕掛け人であってほしい。 と述べました。
印象として、第4分科会は会場からの質問や意見が思いのほか少なかったので
もう少し、この機会を生かして県内外の取り組みを
積極的に取り入れたり、交換する部分があれば良かったのではということが
課題か、と思いました。


会場は中央公民館のサークルの方の作品が並べられ、にぎやかでした。
沖縄のお菓子も準備されており、会場はあたたかい雰囲気でした。


2日目のシンポジウムは県立武道館で開催されました。
900名近い参加者だったようです。
開会式の前に那覇市立壷屋小学校児童による「組踊」がありました。

テーマを「島に根ざそう」とし、
うちな~噺家の藤木勇人氏より記念講演が行われました。
毎年全国ニュースで取り上げられる、那覇の成人式の荒れた様子の報道に触れ、
あれはほんの一面であり、その後ろからごみを拾っている若者がいることや
公民館で開催する成人席は荒れていないことなど、
そのほかにも、沖縄県のイメージとその「ホントのところ」をユーモアを交え話してくださいました。
会場入り口には、沖縄のお菓子の振る舞いコーナーがあり、
心づかいが県外からの参加者にも伝わったのではないでしょうか。

さて、
私は取材ということもあり、最後列で聞いていたのですが、
なんと、残念ながら音割れで聞き取れない部分が多かったです。。
耳に手をかざして耳をすます人が何人もいて、私もしばらくはそうしていました。
しかし、いまいち聞こえない部分は多かったのは残念です。
そのせいだけではないと思うのですが、
半分から後方の方のマナーが非常に気になりました。
途中退席者や床の音に配慮せず大きな音でうろうろする人、
携帯電話の着信音や携帯電話で話す人、
デジタルカメラのデジタル音を何度も鳴らす人など、
エッ?と思うような光景がありました。
若者を公民館に参加させたい、というようなことが多く聞かれる二日間でしたので
ちょっとこれではそんなこと言えるでしょうか・・・と。
憧れられる大人をまずは目指したい、と思いながら会場を後にしました。。
また、1日目の分科会のまとめについて、少しであっても
分かち合いの時間があれば、さらに良かったのではと思いました。
2010年11月10日
我喜屋監督から学ぶ「心の教育」11/22(月)
高校野球史上6校目の「春夏制覇」という偉業を達成し、
同時に「沖縄県勢初の夏の甲子園優勝」という偉業を達成した人と言えば・・
言わずと知れた、あの我喜屋監督。
野球指導を通した人間教育を我喜屋監督より学び、自己の人格を磨き、
豊かな人生を送るための学習の機会とする ことを趣旨に
那覇市石嶺公民館にて講演会があります。
先日、浦添市の社会教育研究大会にて
私は一足先に我喜屋監督のお話を聞いてまいりました。
ユーモアを交えた、非常にわくわくする時間でした。
この夏、高校野球に燃えた方も、野球に詳しくない方も、
野球がスポーツの枠を超えた、
社会に出てからの人格形成の基本について
きっと学びがある・・と思います。
私は、「へぇ~」の連続でした。お勧めです。
平成22年度那覇市石嶺公民館市民講座
(おきなわ県民カレッジ連携講座)
主催:那覇市石嶺公民館
講師:興南学園 理事長・野球部監督 我喜屋 優監督
11月22日(月)19時~21時
那覇市石嶺公民館2階ホール
対象:高校生以上、那覇市内在住、在勤、在学の方
受講料:無料
定員:100名(先着順)
申込期間:11月15日(月)~19日(金)まで
平日9時~17時に直接来館かお電話でお申し込みください。
891-3447
★公共の交通機関をご利用ください。
同時に「沖縄県勢初の夏の甲子園優勝」という偉業を達成した人と言えば・・
言わずと知れた、あの我喜屋監督。
野球指導を通した人間教育を我喜屋監督より学び、自己の人格を磨き、
豊かな人生を送るための学習の機会とする ことを趣旨に
那覇市石嶺公民館にて講演会があります。
先日、浦添市の社会教育研究大会にて
私は一足先に我喜屋監督のお話を聞いてまいりました。
ユーモアを交えた、非常にわくわくする時間でした。
この夏、高校野球に燃えた方も、野球に詳しくない方も、
野球がスポーツの枠を超えた、
社会に出てからの人格形成の基本について
きっと学びがある・・と思います。
私は、「へぇ~」の連続でした。お勧めです。
平成22年度那覇市石嶺公民館市民講座
(おきなわ県民カレッジ連携講座)
主催:那覇市石嶺公民館
講師:興南学園 理事長・野球部監督 我喜屋 優監督
11月22日(月)19時~21時
那覇市石嶺公民館2階ホール
対象:高校生以上、那覇市内在住、在勤、在学の方
受講料:無料
定員:100名(先着順)
申込期間:11月15日(月)~19日(金)まで
平日9時~17時に直接来館かお電話でお申し込みください。
891-3447
★公共の交通機関をご利用ください。
2010年11月10日
明日から九州地区公民館研究大会です。
11月11日(木)12日(金)は
第61回九州地区公民館研究大会 沖縄大会です。
9日、いくつかの公民館に行ったのですが
どこも準備に大わらわでした。
お忙しいところお邪魔しました。
写真は那覇市中央公民館の入口に飾ってあった
色々な組み合わせの折りヅルです。(スゴイ!)
2010年11月02日
【第3期生募集】てだこ市民大学
このブログでも何度かご紹介している浦添市で開催の
てだこ市民大学の第3期生募集が始まりました。
2ヵ年制で、平成22年度3月には初の卒業生が誕生します。
その時には是非、インタビューをしてみたいです!
浦添市に在住、在勤、在学している方、必見です。
きっと参加された方は、今まで以上に浦添市が身近に感じられることでしょう。
地域で活躍する仲間が出来るチャンス!?ぜひお申し込みしてはいかがですか?


募集学部・人員:【コミュニティビジネス・地域振興学部】
【健康福祉・スポーツ振興学部】
【文化振興・教養学部】
【地域・学校支援コーディネーター養成学部】
※各学部とも15人
応募資格:満16歳以上で、浦添市内に在住・在勤・在学している方。
健康で意欲のある方。
募集要項配布:11月1日(月)~11月30日(火)
出願期間:12月1日(水)~12月15日(水)
募集要項配布場所:てだこ市民大学事務局(浦添市庁舎7階生涯学習振興課内)
浦添市役所1階総合案内、その他公共施設等
てだこ市民大学の第3期生募集が始まりました。
2ヵ年制で、平成22年度3月には初の卒業生が誕生します。
その時には是非、インタビューをしてみたいです!
浦添市に在住、在勤、在学している方、必見です。
きっと参加された方は、今まで以上に浦添市が身近に感じられることでしょう。
地域で活躍する仲間が出来るチャンス!?ぜひお申し込みしてはいかがですか?


募集学部・人員:【コミュニティビジネス・地域振興学部】
【健康福祉・スポーツ振興学部】
【文化振興・教養学部】
【地域・学校支援コーディネーター養成学部】
※各学部とも15人
応募資格:満16歳以上で、浦添市内に在住・在勤・在学している方。
健康で意欲のある方。
募集要項配布:11月1日(月)~11月30日(火)
出願期間:12月1日(水)~12月15日(水)
募集要項配布場所:てだこ市民大学事務局(浦添市庁舎7階生涯学習振興課内)
浦添市役所1階総合案内、その他公共施設等
2010年11月01日
研究紀要第5号「生涯学習フォーラム」原稿の募集(琉球大学)
琉球大学生涯学習教育研究センターで発行5回目となる
「生涯学習フォーラム」第5号の原稿募集が始まっています。
◆ ◆ ◆ ◆
以下、琉球大学生涯学習教育研究センターより------------------
地域のボランティアやNPO、自治体などによる生涯学習支援の実践報告や、
沖縄県の生涯学習振興に資する全国的な取り組みの紹介、
生涯学習に関する研究論文など、幅広く募集しております。
第5号の原稿締め切りは平成23年1月31日となっております。
数多くの投稿をお待ちしております。
投稿規程および編集規程
http://www.ercll.u-ryukyu.ac.jp/magazine/index.cgi
-----------------------------------------------------------------------------------
こちらから、過去の紀要もご覧いただけます。
とても勉強になりますのでおすすめです。
↓ ↓
http://www.ercll.u-ryukyu.ac.jp/magazine/index.cgi
「生涯学習フォーラム」第5号の原稿募集が始まっています。
◆ ◆ ◆ ◆
以下、琉球大学生涯学習教育研究センターより------------------
地域のボランティアやNPO、自治体などによる生涯学習支援の実践報告や、
沖縄県の生涯学習振興に資する全国的な取り組みの紹介、
生涯学習に関する研究論文など、幅広く募集しております。
第5号の原稿締め切りは平成23年1月31日となっております。
数多くの投稿をお待ちしております。
投稿規程および編集規程
http://www.ercll.u-ryukyu.ac.jp/magazine/index.cgi
-----------------------------------------------------------------------------------
こちらから、過去の紀要もご覧いただけます。
とても勉強になりますのでおすすめです。
↓ ↓
http://www.ercll.u-ryukyu.ac.jp/magazine/index.cgi
2010年10月26日
広報誌7号を発行しました。
広報誌「社会教育の風 沖縄から」7号と
9月10日に開催した座談会をまとめたものを発行しました。
本日から随時発送いたしますので、今しばらくお待ちください。
発送する広報誌は白黒印刷なのですが、
こちらからはカラーでダウンロード出来ますので、ぜひどうぞ。
広報誌「社会教育の風 沖縄から」7号(全4ページ)
PDFが開きます。
P1>>
P2>>
P3>>
P4>>

座談会報告特別号(全12ページ)
PDFが開きます>>

8月に発行した広報誌6号はこちら>>
9月10日に開催した座談会をまとめたものを発行しました。
本日から随時発送いたしますので、今しばらくお待ちください。
発送する広報誌は白黒印刷なのですが、
こちらからはカラーでダウンロード出来ますので、ぜひどうぞ。
広報誌「社会教育の風 沖縄から」7号(全4ページ)
PDFが開きます。
P1>>
P2>>
P3>>
P4>>

座談会報告特別号(全12ページ)
PDFが開きます>>

8月に発行した広報誌6号はこちら>>
2010年10月22日
第52回全国社会教育研究大会(福島大会)10/27-29

第52回全国社会教育研究大会(福島大会)が開催されます。
○趣旨
現在、私たちには、急速な時代の変化に対応するため、知識や技術のみならず、豊かな人間性を含む総合的な「知」が必要であるといわれている。そのためには、地域住民一人一人が生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成果を適切に生かすこと のできる社会の必要性や重要性が叫ばれ、実現に向けての要請や期待がますます高まっている。
一方、厳しい経済状況において、地方分権が進む中、行政改革や規制緩和などにより、これまで行政が提供してきた地域におけるサービスの縮小も進んでいることから、地域住民どうしが、一層、信頼関係を築き、地域に対する誇りや愛情を持ち、地域の良さを次の世代に引き継いでいく、自立 した地域社会を形成することが重要であり、地域社会全体の教育力向上のさらなる取組みへの要請
も高まっている。
このような「社会の要請」にこたえ、地域住民の様々な経験や知識等が、社会において共有、継承され、さらに新たな創造、工夫が生み出される、いわゆる「知の循環型社会」を構築するため、社会教育の一層の振興が必要である。
このような中、全国の社会教育委員等が一堂に会し、各地域における社会教育活動の状況や研究成果等の情報を交換し、生涯学習社会の実現をめざした社会教育の今日的課題の解決方法及び社会教育委員の果たすべき役割等についての研究協議を開催することは、新しい時代を切り拓き、「社会の要請」にこたえる社会教育の一層の振興に資することを信じるものである。
○大会スローガン
「うつくしま、ふくしま発。地域が元気になる社会教育!」
○研究主題
「継承」と「創造」が循環する地域社会をつくる社会教育振興のあり方
○期日
平成22年10月27日(水)~29日(金)
○参加者
都道府県・政令指定都市・区市町村の社会教育委員及び社会教育関係者
生涯学習・社会教育に関心のある方 (どなたでも参加できます)
○会場
福島県郡山市熱海町 郡山ユラックス熱海、ホテル華の湯
○参加料
一人 5,000円
○主催
社団法人 全国社会教育委員連合
東北地区社会教育委員連絡協議会
福島県市町村社会教育委員連絡協議会
第52回全国社会教育研究大会福島大会実行委員会
福島県教育委員会
郡山市教育委員会
○後援 (順不同)
文部科学省
財団法人 全日本社会教育連合会
青森県教育委員会 岩手県教育委員会 宮城県教育委員会
秋田県教育委員会 山形県教育委員会
福島県 郡山市
福島県市長会 福島県町村会
福島県市町村教育委員会連絡協議会
福島県都市教育長協議会 福島県町村教育長協議会
福島県小学校長会 福島県中学校長会
福島県高等学校長協会 福島県PTA連合会
福島県高等学校PTA連合会 福島県特別支援学校PTA連合会
福島県婦人団体連合会 福島県連合青年会
福島県公民館連絡協議会 福島県子ども会育成会連合会
福島県商工会連合会 郡山コンベンションビューロー
新“うつくしま、ふくしま。”県民運動推進会議
福島民報社 福島民友新聞社 朝日新聞福島総局
毎日新聞福島支局 読売新聞東京本社福島支局
産経新聞福島支局 河北新報社 日本経済新聞社福島支局
時事通信社福島支局 共同通信社福島支局
NHK福島放送局 ラジオ福島 福島テレビ 福島中央テレビ
福島放送 テレビュー福島 ふくしまFM
○大会日程
・1日目 10月27日(水)
15:00~17:00 社団法人 全国社会教育委員連合 第2回理事会
・2日目 10月28日(木)
10:00~11:30 社団法人 全国社会教育委員連合 第2回総会
11:30~12:30 受付
12:30~13:30 開会行事
開会宣言
主催者あいさつ
表彰 他
13:30~15:00 基調講演
講師 佐藤 安太 氏 (株式会社タカラトミー創業者)
15:00~15:30 アトラクション
郡山市立郡山第二中学校 管弦楽部
(平成16年・18年 全国学校合奏コンクール 最優秀賞)
15:30~17:00 シンポジウム
◆パネラー
NPO法人スクール・アドバイス・ネットワーク 理事長 生重 幸恵 氏
前 国立オリンピック記念青少年総合センター 所長 本木 光史 氏
日本青年団協議会 会長 吉田 恵三 氏
◆コーディネーター
茨城大学 名誉教授 菊池 龍三郎 氏
17:00~ 全体会・閉会行事
次期開催地あいさつ
閉会宣言
~18:00 分科会打合せ会
18:00~ 懇親会
・3日目 10月29日(金)
9:00~ 9:30 受付
9:30~ 分科会(部会ごとに解散)
○第1分科会 家庭教育支援
[テーマ]
・社会全体で家庭教育を支援する仕組みづくりのあり方
[主な研究・討議の視点]
① 子育てに関する悩みや問題を抱える親や保護者が、気軽に相談
できるための地域における仕組みをどのようにつくればよいか。
② 親として必要な知識や技術などを学ぶ機会や場を、地域住民等
の協力を得ながらどのようにつくればよいか。
[事例提供者(予定)]
① 青森県 五所川原市
② 鳥取県 米子市
[会場]
・郡山ユラックス熱海 ホテル華の湯
○第2分科会 地域の教育力の向上
[テーマ]
・学校、家庭、地域住民の連携・協力のあり方
[主な研究・討議の視点]
① 青少年の社会性や自立心をはぐくむための地域の教育力として
の支援のあり方はどうあればよいか。
② 地域の子どもは地域で育てるための、学校、家庭、地域住民の
連携・協力の促進はどうあればよいか。
[事例提供者(予定)]
① 千葉県 八街市
② 宮城県 利府町
[会場]
・郡山ユラックス熱海 ホテル華の湯
○第3分科会 生涯学習の振興
[テーマ]
・人づくり、まちづくりをめざした地域における生涯学習振興のあり方
[主な視点]
① 地域の教育資源を生かし、地域住民が集い、学び、つながるた
めの生涯学習の振興のあり方はどうあればよいか。
② 身近な地域社会を単位とした、地域住民の生涯学習による地域
コミュニティーの構築のあり方はどうあればよいか。
[事例提供者(予定)]
① 北海道 恵庭市
② 岩手県 金ヶ崎町
[会場]
・郡山ユラックス熱海 ホテル華の湯
○第4分科会 社会教育委員の役割
[テーマ]
・地域の特色や伝統を未来につなぐ社会教育委員のあり方
[主な視点]
① 地域を見直し、地域の良さを掘り起こすための社会教育委員の
会議の活性化はどうあればよいか。
② 自立した地域社会づくりのための社会教育委員としての役割は
どうあればよいか。
[事例提供者(予定)]
① 鹿児島県 指宿市
② 石川県 中能登町
[会場]
・郡山ユラックス熱海 ホテル華の湯
○第5分科会 社会教育施設
[テーマ]
・住民の学習拠点としての社会教育施設のあり方
[主な視点]
① 住民のニーズや地域課題にこたえ、学習拠点となる社会教育施
設はどうあればよいか。
② 地域の関係機関等と連携し、地域づくりをめざした住民参画に
よる事業の展開はどうあればよいか。
[事例提供者(予定)]
① 青森県 平川市
② 福島県 郡山市
[会場]
・郡山ユラックス熱海 ホテル華の湯
○大会ホームページ
http://www.syakai.fks.ed.jp/22zensyaken/zenkoku.html
○事務局
第52回全国社会教育研究大会(福島大会)実行委員会 事務局
〒960-8688 福島県福島市杉妻町2番16号
福島県教育庁社会教育課内
TEL : 024-521-7799 FAX : 024-521-7974
e‐mail : seki.tadaaki@er51.fks.ed.jp
【担当 : 関 ・ 木村】
2010年10月20日
第34回浦添市社会教育研究大会(11/5)
11月5日(金)
第34回浦添市社会教育研究大会が開催されます。
もう定員いっぱいだそうですが、非常に興味深い内容ですのでお知らせします。
浦添市は今年度から「親学」に力を入れています。
------------------------------------------------------------------------

◆テーマ「親学で、より良い地域社会の実現を」
会場:浦添市男女共同参画推進 ハーモニーセンター1階ホール
講演 興南学園理事長・野球部監督 我喜屋 優 氏
演台 「高校野球を通した人間力の形成」
受付 午後1時 講演 午後1時半
◆シンポジウム 午後3時~4時20分
テーマ「子育ては、親育て」
コーディネーター 浦添市教育委員会社会教育指導員 与那覇律子 さん
パネリスト
生涯学習振興課長 新崎 寛治 氏 (行政の立場から)
仲西幼稚園 教諭 興那覇 純 氏 (教育の現場から)
仲西小学校保護者 知念 賢世 氏 (父親の立場から)
港川小学校保護者 三輪 華江子氏 (母親の立場から)
主催:浦添市教育委員会生涯学習振興課 電話098(876)1234 内線6062
第34回浦添市社会教育研究大会が開催されます。
もう定員いっぱいだそうですが、非常に興味深い内容ですのでお知らせします。
浦添市は今年度から「親学」に力を入れています。
------------------------------------------------------------------------

◆テーマ「親学で、より良い地域社会の実現を」
会場:浦添市男女共同参画推進 ハーモニーセンター1階ホール
講演 興南学園理事長・野球部監督 我喜屋 優 氏
演台 「高校野球を通した人間力の形成」
受付 午後1時 講演 午後1時半
◆シンポジウム 午後3時~4時20分
テーマ「子育ては、親育て」
コーディネーター 浦添市教育委員会社会教育指導員 与那覇律子 さん
パネリスト
生涯学習振興課長 新崎 寛治 氏 (行政の立場から)
仲西幼稚園 教諭 興那覇 純 氏 (教育の現場から)
仲西小学校保護者 知念 賢世 氏 (父親の立場から)
港川小学校保護者 三輪 華江子氏 (母親の立場から)
主催:浦添市教育委員会生涯学習振興課 電話098(876)1234 内線6062
2010年10月20日
沖縄県「文字・活字文化の日」記念フォーラム
11月5日(金)に
沖縄県教育委員会主催の
「文字・活字文化の日」記念フォーラムが開催されます。
http://www.lll-okinawa.info/cgi-bin/welbbs_i/community.cgi?cmd=one;no=1781;id=
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
読書の秋!10月27日は「文字・活字文化の日」
10月27日~11月9日は「秋の読書週間」です。
読書に最適なこの時季に、読書の大切さ、楽しさについて
共に考えてみませんか。
とき:平成22年11月5日(金)13:45~17:00(受付13:00~13:30)
場所:沖縄県総合福祉センター(ゆいホール)
参加対象:公立図書館、公民館図書館及び児童館職員
読書活動団体、学校関係者等
1、読書活動優秀実践者表彰
学校、図書館、団体及び個人
2、講演
「読む力を鍛え、想像力を膨らませる~読み語りの世界~」
講師:高見知佳(タレント)
3、シンポジウム
伝えたい想いを文字にのせて~読書県おきなわを目指して~
コーディネーター:上原 明子(沖縄キリスト教短期大学教授)
シンポジスト: 大城貞俊(作家、琉球大学教育学部准教授)
新城和博(沖縄県産本編集者、(有)ボーダーインク勤務)
大田 守(前沖縄県PTA連合会長)
国吉 綾子(前沖縄県立図書館資料課長)
沖縄県教育委員会主催の
「文字・活字文化の日」記念フォーラムが開催されます。
http://www.lll-okinawa.info/cgi-bin/welbbs_i/community.cgi?cmd=one;no=1781;id=
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
読書の秋!10月27日は「文字・活字文化の日」
10月27日~11月9日は「秋の読書週間」です。
読書に最適なこの時季に、読書の大切さ、楽しさについて
共に考えてみませんか。
とき:平成22年11月5日(金)13:45~17:00(受付13:00~13:30)
場所:沖縄県総合福祉センター(ゆいホール)
参加対象:公立図書館、公民館図書館及び児童館職員
読書活動団体、学校関係者等
1、読書活動優秀実践者表彰
学校、図書館、団体及び個人
2、講演
「読む力を鍛え、想像力を膨らませる~読み語りの世界~」
講師:高見知佳(タレント)
3、シンポジウム
伝えたい想いを文字にのせて~読書県おきなわを目指して~
コーディネーター:上原 明子(沖縄キリスト教短期大学教授)
シンポジスト: 大城貞俊(作家、琉球大学教育学部准教授)
新城和博(沖縄県産本編集者、(有)ボーダーインク勤務)
大田 守(前沖縄県PTA連合会長)
国吉 綾子(前沖縄県立図書館資料課長)
2010年10月18日
佐賀県に行ってきました。
10月14日(木)15日(金)に
平成22年度 第40回
九州ブロック社会教育研究大会 佐賀大会に参加しました。
沖縄県からは17名で参加してまいりました。
初日は分科会、2日目は全体会として、シンポジウムが開催されました。
第1分科会 テーマ「家庭教育・子育て支援」
第2分科会 テーマ「地域教育力の充実」
第3分科会 テーマ「社会教育委員の役割」
第4分科会 テーマ「社会教育行政・公民館の役割」
私は第3分科会に参加しました。

会場いっぱいの参加者で、質疑応答の時間もぎりぎりまで発言が続きました。
課題はどこの地域も似ており、
予算の削減に悩みつつも工夫で乗り切りたいということや、
行政に任せきりではなく、自主的に考え、行動していくことの重要さなどを確認しました。
この会場に参加したのは全体の3分の1の人数だそうで、
「社会教育委員の役割」というテーマへの関心の高さがうかがえます。
沖縄県から参加したメンバーも質問を盛んにしておられました。

島尻地区社会教育委員連絡協議会会長 久保田さん 質問中

浦添市 社会教育委員 長田さん 発言中

2日目のシンポジウムのテーマは
「社会教育、これまでの軌跡、これからの針路」~社会教育委員の果たすべき役割~
と題し、開催されました。
次号広報誌にてご報告します。
また、次年度は沖縄で開催されるということもあり、沖縄大会の詳細も発表されました。
研究テーマは
「教育新時代に対応する社会教育」
~新しい公共の観点にたち、地域の特性を生かした地域コミュニティの形成と社会教育の役割~

期日 平成23年11月10日(木) 分科会
11日(金) 記念講演
開催地 沖縄県那覇市
参加対象
九州各県・各市町村の社会教育委員、社会教育関係者、
生涯学習・社会教育に関心のある方
沖縄県社会教育委員連絡協議会会長
藏根 芳雄さんから来年度沖縄大会について
あいさつされました。
社会教育に関わるみなさま、一年間一緒に盛り上げてゆきましょう!
平成22年度 第40回
九州ブロック社会教育研究大会 佐賀大会に参加しました。
沖縄県からは17名で参加してまいりました。
初日は分科会、2日目は全体会として、シンポジウムが開催されました。
第1分科会 テーマ「家庭教育・子育て支援」
第2分科会 テーマ「地域教育力の充実」
第3分科会 テーマ「社会教育委員の役割」
第4分科会 テーマ「社会教育行政・公民館の役割」
私は第3分科会に参加しました。

会場いっぱいの参加者で、質疑応答の時間もぎりぎりまで発言が続きました。
課題はどこの地域も似ており、
予算の削減に悩みつつも工夫で乗り切りたいということや、
行政に任せきりではなく、自主的に考え、行動していくことの重要さなどを確認しました。
この会場に参加したのは全体の3分の1の人数だそうで、
「社会教育委員の役割」というテーマへの関心の高さがうかがえます。
沖縄県から参加したメンバーも質問を盛んにしておられました。

島尻地区社会教育委員連絡協議会会長 久保田さん 質問中

浦添市 社会教育委員 長田さん 発言中

2日目のシンポジウムのテーマは
「社会教育、これまでの軌跡、これからの針路」~社会教育委員の果たすべき役割~
と題し、開催されました。
次号広報誌にてご報告します。
また、次年度は沖縄で開催されるということもあり、沖縄大会の詳細も発表されました。
研究テーマは
「教育新時代に対応する社会教育」
~新しい公共の観点にたち、地域の特性を生かした地域コミュニティの形成と社会教育の役割~

期日 平成23年11月10日(木) 分科会
11日(金) 記念講演
開催地 沖縄県那覇市
参加対象
九州各県・各市町村の社会教育委員、社会教育関係者、
生涯学習・社会教育に関心のある方
沖縄県社会教育委員連絡協議会会長
藏根 芳雄さんから来年度沖縄大会について
あいさつされました。
社会教育に関わるみなさま、一年間一緒に盛り上げてゆきましょう!
2010年10月08日
てだこ市民大学2
浦添市で開設されている「てだこ市民大学」の講座を
一つ見学させていただきました。
(てだこ市民大学の概要はこちら>>)

今回は、10月7日(木)19:30~
コミュニティ・ビジネスの地域振興学部1年次の
「経営と地域経済概論」でした。
講師は、沖縄キリスト教学院大学の北原秋一さんでした。
受講生は7名という少人数で、講師と近く和気あいあい。
みなさん、浦添市在住ということで、浦添市をこれからどうしていくか、
という視点で真剣に受講されていました。
一つ見学させていただきました。
(てだこ市民大学の概要はこちら>>)

今回は、10月7日(木)19:30~
コミュニティ・ビジネスの地域振興学部1年次の
「経営と地域経済概論」でした。
講師は、沖縄キリスト教学院大学の北原秋一さんでした。
受講生は7名という少人数で、講師と近く和気あいあい。
みなさん、浦添市在住ということで、浦添市をこれからどうしていくか、
という視点で真剣に受講されていました。