2011年02月09日
那覇地区社会教育委員連絡協議会
平成22年度那覇地区社会教育委員連絡協議会が
開催されました。
期日:平成23年1月27日(木)14:00~17:00
テーマ:「地域ぐるみで育てよう」~子育ては親育て~
場所:浦添市男女共同参画推進ハーモニーセンター 2階第1会議室
●趣 旨:地区内の社会教育委員をはじめ、社会教育行政関係者が一堂に会し、現在の社会教育における様々な今日的な課題等の解決や社会教育振興のための研究等を行うことにより、地区内各市町村の社会教育の充実を図るとともに、会員相互の親睦、情報交換を行うことを目的に研修会を行う。
【内容】
まずはじめに、
10月に佐賀県で開催された「第40回記念九州ブロック社会教育研究大会」
についての報告が、浦添市社会教育委員の長田隆子氏より行われた。
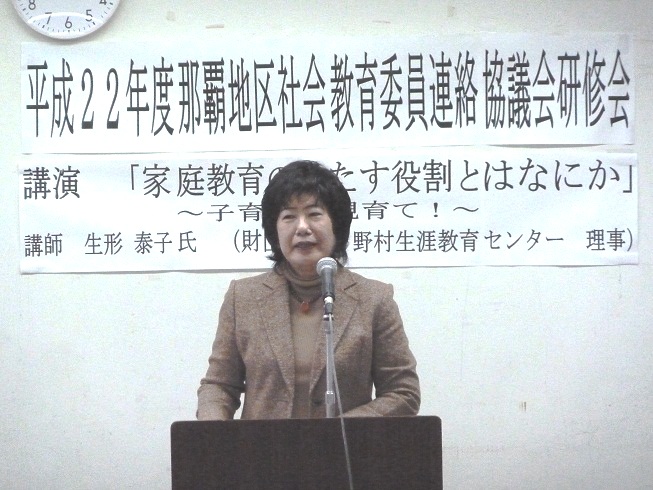
分科会での質疑応答の際、
「事例の実践等を委員自らできるかなではなく、自分の地域ではどういうシステムで、
どういう計画で取り入れることができるか考えることが委員の役割だと考える(長崎県)」
「行動する社会教育委員でありたい(大分県)」という意見を紹介。
シンポジウムの内容も詳しく、参加していない人にもよくわかる発表でした。
私も佐賀県の研究大会で長田さんとおなじ分科会に参加していました。
社会教育に関わる方は、さぁ、次は自分が動く番だ、と心新たにしたのではないでしょうか。
また、「家庭教育の果たす役割とはなにか」~子育ては親育て~と題し、
生形泰子氏(財団法人 野村生涯教育センター)の講演があった。

*次世代に何を残せばよいのか、どう生きるかが問われている時代であり社会教育委員の果たす役割は大きい。
*「何のために生きているのか」が見えない人が多く、人間関係が希薄でなにもかもインターネットで完結しようとする傾向がある。物は豊かになったが、心は貧しくなるばかりだ。情報量が増えたことにより、主体性が失われ、情報に流される選択をする人が増えている。
*「己がどう生きるのか、そこによりよい発展はあるのか、社会への還元ということで社会教育委員は動いている」とした。
子育てをしていた当時、野村生涯教育センターにて「良い子を育てるためにはどうしたらよいか」と聞くと、
「お母さんが変わらなければ変わりません」と言われたエピソードを披露し、
教えるものこそ学ばなければならないと述べた。
家庭は親子の教育の最大の場であり、無償の愛がその後、何があろうと子どもに乗り越えさせる力をつける.
受け身(育てなければならない)では何もできない、親が何に価値を置くかを子どもは生活の中で見ている。
自分で長い命を育てることのできる育児は楽しいものである。
思わず引き込まれるお話で、笑いあり、苦笑あり?の楽しい講演でした。

開催されました。
期日:平成23年1月27日(木)14:00~17:00
テーマ:「地域ぐるみで育てよう」~子育ては親育て~
場所:浦添市男女共同参画推進ハーモニーセンター 2階第1会議室
●趣 旨:地区内の社会教育委員をはじめ、社会教育行政関係者が一堂に会し、現在の社会教育における様々な今日的な課題等の解決や社会教育振興のための研究等を行うことにより、地区内各市町村の社会教育の充実を図るとともに、会員相互の親睦、情報交換を行うことを目的に研修会を行う。
【内容】
まずはじめに、
10月に佐賀県で開催された「第40回記念九州ブロック社会教育研究大会」
についての報告が、浦添市社会教育委員の長田隆子氏より行われた。
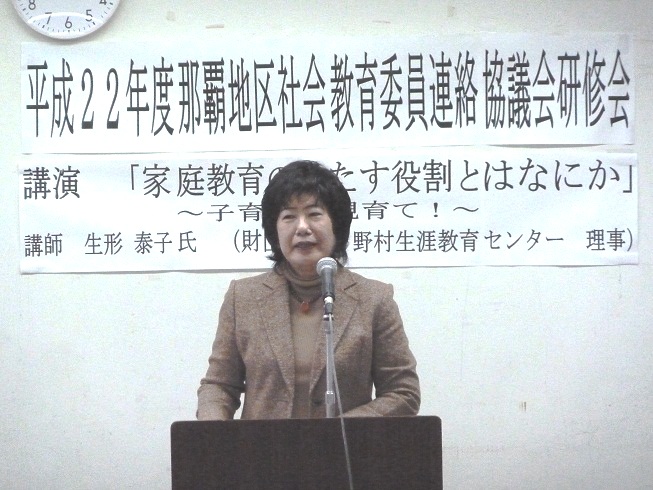
分科会での質疑応答の際、
「事例の実践等を委員自らできるかなではなく、自分の地域ではどういうシステムで、
どういう計画で取り入れることができるか考えることが委員の役割だと考える(長崎県)」
「行動する社会教育委員でありたい(大分県)」という意見を紹介。
シンポジウムの内容も詳しく、参加していない人にもよくわかる発表でした。
私も佐賀県の研究大会で長田さんとおなじ分科会に参加していました。
社会教育に関わる方は、さぁ、次は自分が動く番だ、と心新たにしたのではないでしょうか。
また、「家庭教育の果たす役割とはなにか」~子育ては親育て~と題し、
生形泰子氏(財団法人 野村生涯教育センター)の講演があった。
*次世代に何を残せばよいのか、どう生きるかが問われている時代であり社会教育委員の果たす役割は大きい。
*「何のために生きているのか」が見えない人が多く、人間関係が希薄でなにもかもインターネットで完結しようとする傾向がある。物は豊かになったが、心は貧しくなるばかりだ。情報量が増えたことにより、主体性が失われ、情報に流される選択をする人が増えている。
*「己がどう生きるのか、そこによりよい発展はあるのか、社会への還元ということで社会教育委員は動いている」とした。
子育てをしていた当時、野村生涯教育センターにて「良い子を育てるためにはどうしたらよいか」と聞くと、
「お母さんが変わらなければ変わりません」と言われたエピソードを披露し、
教えるものこそ学ばなければならないと述べた。
家庭は親子の教育の最大の場であり、無償の愛がその後、何があろうと子どもに乗り越えさせる力をつける.
受け身(育てなければならない)では何もできない、親が何に価値を置くかを子どもは生活の中で見ている。
自分で長い命を育てることのできる育児は楽しいものである。
思わず引き込まれるお話で、笑いあり、苦笑あり?の楽しい講演でした。

Posted by 学振 at 09:56│Comments(0)
│報告
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。















